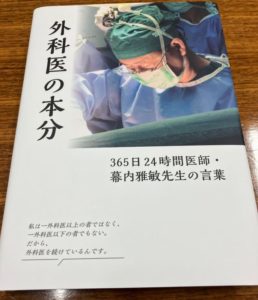正月に「恩師」の自分史を読む
年明け早々、1冊の本が届いた。新聞社に勤務していた時の上司(以後、Mさん)が自費出版した「自分史」だ。まさに、「ブンヤ」と呼ぶにふさわしい新聞記者だった。政界に深く食い込み、競争相手の他社の新聞記者を「きりきり舞い」させた。「親分肌」で、慕う後輩は数知れず。毎年のように、こよなく酒を愛するMさんを囲む会が開かれた。お屠蘇気分が抜けない中、「恩師」の自分史を読んだ。
Mさんと出会ったのは、北海道・根室に赴任した1986年の春だった。入社して初めての転勤。根室に向かう前、緊張しながら北海道支社を訪ねた。右手を挙げながら、穏やかな表情で「よお! 君が櫻井君か」と気さくに語り掛けてくれた。一気に、その人柄に引きずり込まれた。
「根室は北方領土問題を抱える取材の拠点だ。ソ連(現在、ロシア)の諜報機関(KGB)からの誘惑もある。2年後には必ず異動させる。君の活躍を見ているぞ。それまで、頑張れ!」
この言葉に気をよくして、根室ならではの「闇の世界」を明らかにしていった。Mさんは気前よく「報道部長賞」を奮発してくれた。嬉しかった。さらに、取材活動にのめり込んだ。
新聞記者は数年おきに、全国規模の異動がある。勤務地が異なってもMさんとの年賀状のやり取りは続いた。東京で開いたMさんを囲む会に参加すると、同じように右手を挙げながら、「櫻井君、頑張っているか」と声を掛けてくれた。
自分史には、夜討ち朝駆けを繰り返した政治部での、「奮戦記」が書かれていた。三木武夫、田中角栄、大平正芳、福田赳夫といった首相経験者の名前がポンポンと飛び出す。まさに、「自民党戦国史」と呼ぶに相応しい記述が満載だ。
Mさんは以前、こんな自慢話をしてくれたことがある。
「モスクワで日ソ首脳会議を取材した時の事だ。朝刊1面トップに1本の特ダネ記事を書いた。日本で朝刊が配られる時間(モスクワでは深夜)に、取材拠点にしていたモスクワのホテル廊下を、他社の記者たちがバタバタと走り回る足音が聞こえてきた。政治部記者の醍醐味を味わった」
最近は、政治が「ショー」となり、口先が達者で、テレビ映えのいい政治家、パフォーマンスの出来る政治家が人気を集めていることに、苦言を呈する。「嘘の部分が陳列され、本来の、政治の本質は一向に浮かび上がってこない」と書き加えている。
さらに、読み進めると、Mさんの人間性を感じる箇所があった。「日夜、新聞紙面を支えているのは政治部、経済部、社会部、外報部といった華々しい舞台に咲く記者ばかりではない。地方を任された地方記者たちの汗こそが、日常の紙面を支えている」との記述だ。
大手新聞社はどこも、複数の記者がいる県庁所在地の支局(現在は総局)と準支局、一人で勤務する「通信局(または通信部)」と呼ぶ取材拠点があった。通信局の記者は取材エリア内の事件、事故、選挙、街ダネなどをすべて1人でこなさなければならない。大事件・大事故が発生すれば、それこそ右往左往の大忙しだ。新聞記者としての力量が一気に問われる。その一方で、地味な取材活動も多い。東京本社の政治部や社会部の記者と比べると……。複雑な気持ちにもなる。「泣き笑い」の連続だ。Mさんは、こうも書く。
「地方記者は地道な努力を積み重ねていく。政治部記者、社会部記者に勝っても劣らない記者の生き様がそこにはある」
Mさんは東京本社で地方担当部長の時、席を温めることはなかった。地方の支局、準支局、通信局を何度も訪れた。地方記者の喜びや悲哀を聞いて回った。駆け出しのころ、雪深い青森県・津軽地方にあった通信局に駐在したことがある。東京本社から編集局長や担当部長が来た。緊張したが、大いに勇気づけられた。
自分史を読み終え、Mさんの懐の深さを感じた。改めて、人間として、または新聞記者として、忘れてはならない「心構え」を教えられた気がした。
数年前、多くの「人間ドラマ」を書いてきたMさんは多くの記者仲間に送られて旅立った。最後のページを閉じた後、自分史をそっと書棚に置いた。そして、手を合わせて冥福を祈った。
2026年1月15日