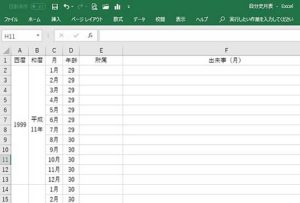浮き上がれ、魔球

砂蒸し温泉からほど近い神社境内が小学生の自分等の遊び場であった。境内の一角にはアコウの木が鳥居の高さをはるかに超えて伸び、広範囲に濃密な樹陰を作り出していた。クーラーはおろか扇風機すらそれほど普及していなかった時代、夏休みともなれば、境内で遊び、アコウの緑陰や張り出した枝に寝そべり本や漫画を読むのが日課だった。漫画「ゲゲゲの鬼太郎」が「墓場鬼太郎」という名称で刊行されており、確か鬼太郎のかあさんも登場していたと思うが、この緑陰で刺激的な恐怖に満ちた当時の独特の水木ワールドをむさぼり読んだ。
炎天下の境内で、仲間と軟式テニスのボールを使用したピッチャー、竹バットのバッターそして本殿への10段ほどの石段の最下段に腰を下ろしたキャッチャー及び外野の四者で遊んだ夏の日々を思い出す。打たれたピッチャーは外野に回り、現外野は石段に腰かけたキャッチャーの最後尾に腰を下ろす。打ったバッターはそのまま。三振すれば外野へ。一番下のキャッチャーがピッチャーになり対戦。そして、真夏の炎天下熱戦が続く。
夏休みのある日、その時私がピッチャーだった。バッターは中学生の先輩。テニスのゴムボールは少し空気が抜け指が引っ掛かり投げやすくなっていた。
私は石段に座る同級生の胸元めがけ投げた。私の目に映ったのは、バッターの手前から浮き上がり、石段に当たりバッターが驚きの声を上げて空振りする光景だった。自分で信じられなかった。当時少年週刊漫画で魔球を投げる少年を主人公にした物語が熱烈に読まれてはいた。この時、私はまるで魔球を投げる主人公に自分がなっているような錯覚を覚えた。自分は魔球を投げている。正面石段の上の拝殿所から奇跡の力が今自分に降り注ぎ、ボールに作用しているのではないかとさえ思った。
2球目もボールは浮き上がりバッターは空振り。境内に10人くらいいた者は皆私の投げるさまに見入っている。3球目は低く逸れ地面で弾んだ。そして4球目。自分でもストライクゾーンを辿ったと思ったボールが上昇カーブを描き、その軌道の下を竹バットが削いだ。三振。本来ならここで私はピッチャーを交代しバッターボックスに入るところである。
しかし、見物していた一人のおじさんが、次は自分に打たせてと半ば強引にボックスに入った。にこにこ笑いながらボックスに立ったおじさんが、大声をあげて空振りを喫する光景がありありと脳裏に浮かぶ。そして、その時、私の投げる場所の後背のアコウの緑陰に父が立ってみていた。外野の友人が父に「浮き上がる球を投げるんだよ」と話しかけていた。父の柔和な笑みがあった。私は面映ゆかったが、うれしく誇らしかった。
何年もの夏をこの境内で遊び過ごしたはずなのに、この夏休みの日しか明瞭な記憶はない。その夏だけだった。父がいたのは。それから半年後に父は死んだ。
太平洋戦争の兵役、抑留、帰還して私が生まれ2年後離婚、北海道へ単身移住し病を得て帰郷。治療するも悪化して死亡した。何ら残すものはなく、家庭をすら維持することもかなわず、無念の内にこの世を去った。しかし、父はおそらくは私のために家庭を作ろうとした、もう一回生きなおそうとした。そう祈願したに違いない。
私は三振したおじさんの後に入った自分の打席で竹バット一閃。打球は積乱雲を射るように弾け飛び雲の裂け間に驚くほど濃い青がのぞいていた。純白の雲と青が鮮烈に輝いていた。私はそこに躍動する幸せを、家庭を垣間見たのだった。
神社での野球の後、砂蒸し温泉近くの海岸に飛び込み泳いでいた。近くの岩場には高温の温泉が湧き出ており、当時は生息していた小エビを友達と捕獲し、網ごと温泉に浸け食べたこともある。塩味が効いてうまかった。真夏の海岸しか思い浮かばない。おそらくはこの時期周りの全てが輝いていた。
私は昨年の2月に自分史活用アドバイザー認定講座を受講し、登録した。その際、自分が一番輝いていた時期、状況を書くワークがあった。その時は一家4人で奄美大島に赴任し、奄美の純朴な自然の中で暮らした3年間を、仕事と空手と家庭の三位一体で暮らした3年間を、自分の中の最も輝いていた時代と記した。それは嘘ではない。事実である。しかし、幻のようにあの真夏の神社の野球が、父の姿が、海岸線がよみがえる。
父は帰郷して、結核病棟の治療から退院したとき父と同年配の女性が一緒だった。それまでの祖母との生活から夢にまで見た父母のいる家庭生活が始まった。真新しい本のページを繰っていくような新鮮な喜びの日々だった。
しかし、その日々も父の死により2年に満たず終わりを告げた。もう一回新しく生きなおそうとした父とその女性がそれまでの人生の長い労苦の後のこの世での希望を切に求めたにも関わらず。あの神社境内で、「浮き上がる球」を投げた魔球小僧であった時期、海岸道路で正装した父と和服姿の母、私と祖母一家4人で写真屋さんに結婚写真を撮ってもらった。波光きらめく海岸通りで皆晴れやかな顔をしている。神事も宴もなかったが、生き直しを決めた父と私たちの出発だった。海岸通りの潮騒はあの日と変わらず優しさを奏でて過ぎていく。砂蒸しの砂熱と溶け合った海風はいかなる時も新生の夢を持つのだと今も温かく話してくれる。
「浮き上がる球」は、柔らかい軟式テニスボールがやや萎んだくぼみに児童の小さな指が引っ掛かり逆回転しホップしたに過ぎない。なんの変哲もないただの変化球である。しかし、父がいて母がいる私の夢であった「家庭」という当時の私の幸せの象徴であったように思うのである。私にとって神社での「浮き上がる球」は奇跡のようにわずかの時ではあったが私に「家庭」を味あわせてくれた。
海岸通りから始まったそれは、間もなく訪れる父の死によって暗転する。きらびやかなものは暗転する。奇跡は必ず暗転する。積乱雲を射るようにアコウの葉越しに弾けた打球が切り裂いた純白の雲と青の対比も、「浮き上がる球」も暗転する前兆だと思えた。そして、その思いはアドバイザー養成講座でのワークに次に輝いていた奄美の生活を記させた。
年々無意識の内によろず暗転を避ける意識が肥大していく。しかし、私の原点は、わずかばかりの魂の宝庫は、あの夏の日にアコウの木の下で私の姿を見てくれていた余命僅かの父の姿である。人生をもう一回生き直そうと挑んでくれた父の決意である。そのスタートを切った海岸通りである。
そして、永遠なれ「浮き上がる魔球」。